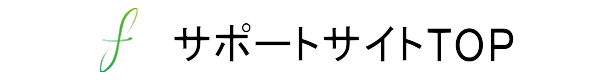スペックって何?
スペックはもともと英語の「specification」を略した「spec」からきています。日本語では「仕様」という意味になります。パソコンの仕様ということは、メーカーがパソコンを開発する際に取り決めた詳しい設計のことですが、端的に表現すれば、パソコンの性能と言うことになります。
例えば、パソコンの画面サイズや重量といった外観で判断できるものから、データの処理速度や記憶領域の容量などの性能も含めて全てスペックと呼ぶことができます。
パソコンのスペックが高いか低いかを判断する基準は、判断する人や状況によって異なるので一概には決められませんが、主に5つ項目に分けることができます。
- OS
- CPU
- メモリ
- HDD/SSD
- 画面サイズ/重量/解像度
各項目のスペックの判断要素と留意点
それぞれの項目でスペックの判断要素となるものや留意点についてみてみましょう。
OS
OSとは「Operating System」の略で、パソコンには必ず入っている最も基本的なソフトウェアで、パソコンのシステム全体を管理し、様々なアプリケーションソフトを動かします。
・OSの種類
現在、市場の大部分のシェアを占めるOSはMicrosoft社のWindowsとApple社のmacOSです。この2つのOSの時代が長く続いてきたのですが、最近ではGoogleからChrome OSを搭載したパソコン「Chromebook」が発売されて注目されています。
こうしたOSの種類が異なっていても、パソコンの基本的な概念には違いはありません。しかし、その特徴や使い勝手などから用途が分かれてきます。Windowsが搭載されたパソコンは家庭やオフィスを問わず広く普及している一方で、Macのパソコンはデザイナーやクリエイターを中心に根強い人気があります。また、Chromebookは低価格なモデルが多く、高度な処理はできなくても普段使いには十分な性能があると評価されています。
・OSのバージョン
OSは新しいバージョンが次々とリリースされてきました。2022年2月現在で最新のOSは、Windowsが「Windows11」Macでは「Monterey」となっています。
なお、Chrome OSは常に最新の状態で使用することが原則で、バージョンを選ぶという概念がありません。強制的に最新のバージョンにアップデートされた状態で使用します。
Windows、Macいずれのパソコンも、古いOSから最新のOSにアップデートも可能ですが、新しいOSに対応していないアプリケーションなどは使えなくなる可能性があります。また、パソコンが新しいOSを稼働するために必要な性能がない場合、処理が遅くなったり、正常に作動しなくなる可能性があるので、アップデートする際は留意するべき点です。
・OSの処理能力
OSに関して確認しておきたいのがbit数です。bit数は一度に扱える情報量の目安のことです。基本的には32bit版と64bit版がありますが、32bit版の場合、32桁の2進数のデータ、つまり、2の32乗の数を一度に処理できることを表します。64bit版であれば、32bit版の2の32乗倍となり処理能力はかなりアップします。現在新しく販売されている製品のほとんどが64bit版となっています。
一般的にアプリを入れる際はパソコンのOSのビット数と同じものを選択するのが好ましいとされます。パソコンが64bit版の場合は、アプリも基本的には64bit版を選択するようにします。
CPU
CPUとは「Central Processing Unit」の略で、別名「プロセッサー」とも言います。パソコンの中心的な役割を果たすもので、具体的にはマウス、キーボード、ハードディスク、メモリー、周辺機器などからデータを受け取り、制御・演算を担当します。CPUはパソコン自体の性能や価格に大きく関わってきます。
CPUは制御部と演算部に分かれます。制御部は、次に処理すべきデータがメモリー上のどのアドレス・番地にあるかをプログラムカウンターというところに記憶し、それを順番に演算部に伝えることにより命令・指令を出します。演算部は、制御部から伝達されたメモリー上のアドレスを手がかりにデータを処理します。
・コアの数
コアはCPUの核の部分であり、制御部と演算部が1セットになっているものです。コアの数が2つ以上あれば同時並行で作業ができます。つまり、コアの数が多いほど同時並行でできる作業も多くなることから、CPUの性能に差が出てきます。コアが2つあるものをデュアルコア、4つあるものをクアッドコア、または複数あるものをマルチコアと呼びます。
・クロック周波数
CPUはクロックという周期的な信号で動作しています。これをクロック周波数(単位はHz)で表しますが、1秒間でどれだけクロックがあるかを意味します。例えば 3GHzのCPUなら、一秒間に約30億回のクロックがあります。クロック周波数が高いほど処理できる回数や量が多くなり、処理スピードが速くなります。
世界初のCPUが発表されたのは1971年でクロック周波数は375KHzでした。各メーカーが次々と新製品を出してクロック周波数は上昇し、わずか2~3年で1000倍のMHzの単位に向上します。2000年にはAMDが世界初の1GHz(=1000MHz)超えを達成し、2008年頃には概ね3.0 GHzを超えました。しかしその後は、4.0GHzを超えるハイエンドなCPUがあるものの、基本的には3.0GHz台で大きく変わっていません。
その背景には、性能を上げるためにクロック周波数を上げようとすると、発生する熱に耐えられないというジレンマがあります。それでもパソコンの性能は大幅に進化しています。それはシングルコアからマルチコアへの移行やプロセスルールの縮小化、命令セットや拡張機能の進歩、内蔵キャッシュメモリの大容量化など、クロック周波数以外の部分の改善により達成しているのです。
・CPUのブランド
CPUを製造している主なメーカーは、Intel社とAMD社が有名です。
IntelのCPUは、現在Core iシリーズとその下位版のPentium、Celeron、AMDは、RyzenシリーズとAthlonが主流となっています。
Intel(デスクトップ)
| Core iシリーズ | Core iシリーズ以前 |
|---|---|
| Core i7(コア数:4~8) | Core 2 Quad(コア数:4) |
| Core i5(コア数:4~6) | Core 2 Duo(コア数:2) |
| Core i3(コア数:2~4) | Pentium D(コア数:2) |
| Pentium(コア数:2) | Pentium 4(コア数:1) |
| Celeron(コア数:1~2) | Celeron D(コア数:1) |
ノートパソコン用のCPUは末尾にU・Y・M・Eが付いていることが多いです。コア数はデスクトップ版とは異なることがあります。
他に、さらに上位のものとしてCore i9、消費電力を抑えたATOM、サーバー向けのXeonなどがあります。
AMD(デスクトップ)
| Ryzenシリーズ | Ryzenシリーズ以前 |
|---|---|
| Ryzen7(コア数:4~8) | A series(コア数:2~4) |
| Ryzen5(コア数:4~6) | FX series(コア数:4~8) |
| Ryzen3(コア数:2~4) | Phenom II(コア数:2~6) |
| Athlon(コア数:2) | Athlon II(コア数:2、4) |
| ー | Phenom(コア数:3、4) |
| ー | Athlon 64 X2(コア数:2) |
他に、上位のCPUとして、Ryzen9、Ryzen Threadripperなどのブランドがあります。また、ノートパソコンにも搭載されていますが、コアの数などは多少異なります。
メモリ
プログラムやデータを記憶・保持するための装置のことです。USBやHDD、昔のフロッピーディスクなども記憶装置ですが、「メモリ」と言う場合は半導体でできたメモリモジュール(メモリIC)を指し、前者を補助記憶装置と呼ぶのに対し、メモリは主記憶装置(メインメモリ)と呼ばれます。
このメインメモリはパソコンのスペックに大きな影響を及ぼします。処理で必要な情報を読み込むと同時にそれらを記録・保持するという役割をします。
また、メモリが十分でないと、データの一時保持にHDDやSSDなどといった補助記憶装置も使うことになるため、その分読み書きの動作に時間がかかってしまいます。処理速度の低下だけでなく、ファイルが開かなかったりパソコンがフリーズしてしまうといった現象もメモリ不足が要因となって起こります。
メモリの代表格はRAMです。RAMはDRAMとSRAMに分類することができます。
| | DRAM | SRAM |
|---|---|---|
| 容量 | 構造がシンプルで 大容量に向いている | 集積化が難しく高密度に ならないため大容量には不向き |
| 処理速度 | 遅い | 非常に高速 |
| データ保持 | リフレッシュが必要で 常に電力消費が行われる | リフレッシュは不要で 消費電力は少ない |
| 価格 | 比較的安価 | 回路が複雑となるため 比較的高価 |
RAMは容量が大きいほど性能は高いと言えます。パソコンで作業をするには一般的には最低4GBが必要です。複数のアプリケーションを開きながら作業をする場合は8GB、高度な動画編集やゲーミングパソコンとして用いる場合は16GBであればストレスを感じないと言われます。ちなみにスマートフォンやタブレットでは1~4GBが普通です。
HDD/SSD
HDDはハードディスクと呼ばれ、パソコン内にあるデータを記憶しておく役割をします。SSDも使い方や用途は同じですが、HDDよりもデータを読み書きするスピードが圧倒的に速く、パソコンの起動時間の短縮などにもなります。
大容量のデータを保管しておく媒体としては長年HDDが使われてきましたが、近年、SSDの容量が大きくなってきたこともあり、急速に普及しつつあります。また、HDDは衝撃に弱い点や消費電力が高いため、最近利用が増えているノートパソコンには向いていません。しかし、SSDよりも安価であったり、1つのドライブで保存できるデータ量が大きいというメリットがあります。
画面サイズ/重量/解像度
・画面サイズと重量
市場で流通している画面サイズは、ノートパソコンだと6~17.3インチ程度までですが、使い勝手としては、11.6、13.3、14、15.6インチあたりのものがよさそうです。また、デスクトップパソコンであれば、19~34インチ程度までのものが流通していますが、21.5、23.8、27インチあたりのものがよく使われているようです。
画面サイズで言うインチは、画面の対角線の長さのことです。1インチ=2.54cmなので、例えば、10インチ液晶の場合、対角線は25.4cmで、その幅と高さはそれぞれ22.1cmと12.5cmになります。
画面が大きいと作業はしやすくなりますがその分重くなるので、特によく持ち運びするノートパソコンなどは考慮した方がよさそうです。
<ノートパソコンの画面サイズと重量の目安>
- 11.6インチ:1kg~1.6kg
- 13.3インチ:1.2kg~1.8kg
- 14インチ:2kg前後
- 15.6インチ:1.6kg~2.6kg
- 17.3インチ:2.4kg~4kg
・解像度
解像度は、画像がどれぐらいの細かさでデジタル化(画素に分割)されているかを単位長さあたりのピクセル(px)数で示したもの、つまり画素の密度です。これが低いと画像はガタガタした粗いものになってしまいます。
画面の解像度にはいくつかの種類があります。
VGAは、横640px、縦480px(「640×480」のように表記する場合もあります)の解像度です。この時の縦横比は「4:3」です。1987年にIBMのパソコンで採用され、しばらく主流になっていましたが、2005年頃からは横長のものが主流となっています。横長の解像度としては、HD(ハイビジョン、1280px:720px)やWXGA (1280px:800px)などがあります。その横長比はそれぞれ「16:9」「16:10」です。
このように、画素の密度は数値が高いほど画面がきめ細やかに見え、より多くの情報量を画面に表示できます。